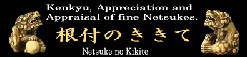| |
■ |
江戸時代の各種の職業を紹介した『人倫訓蒙図集』(元禄3年(1690年)刊行)においては、様々な職業の職人が、分業体制で仕事をしていたことが分かります。この中では、「角細工」として、大きな象牙材から固まりを切り出している職人が紹介されています。
本文では、根付、緒締め、挽き蓋、鉄砲の薬入れ等、角や象牙を用いるたぐいを製作する職人と紹介され、挿絵には、これから根付などに加工される材料の固まりや三味線のバチが描かれています。奥にはろくろ引きの回転装置が見えるので、饅頭根付や鏡蓋根付の台を挽物として加工することも引き受けていたのだと思います。
本資料により、17世紀に既に角細工の専門職人が存在し、象牙根付が製作されていたことが注目されます。角細工職人として本書に記録されるだけの、象牙材の相当な流通が当時からあったと考えられます。
 |
『人倫訓蒙図集』(元禄3年(1690年)刊行)より
|
|
|
|
|
■ |
『嚢物の世界、江戸小物のデザイン 百楽庵コレクション』(求龍堂(1998年10月))によると、ひとつの袋物を製作するための分業図として、「袋物商」の下に、「仕立屋」、「木型屋」(袋物を仕立てるための木型を作る)、「編物屋」、「牙彫師」、「蒔絵師」、「下地屋」(木や紙で筒や根付の下地を作る)、「彫金家」、「煙管屋」、「錺屋(かざりや)」(金、銀、赤銅で裏座、鳩目、小豆鎖などを作る)、「組紐屋」、「刺繍屋」、「裂問屋」、「皮革問屋」といった職人が関与していて、袋物が多くの職人による分業の下での総合芸術であることを示しています。
|
|
■ |
高村光雲の自伝によると、仏師に付属した職業として、彫刻家に適当なサイズの材料を切って渡す木寄師(きよせし)、塗師、錺師といった分業者のことが記されています。
|
|
■ |
その他、様々な資料を確認すると、幕末から明治期・大正期にかけて、浅草、蔵前、浅草橋周辺には、様々な職種の袋物やアクセサリ関係の下職人が集積していたことが分かっています。
|
|
■ |
江戸時代の浮世絵の製作も典型的な分業制です。「絵師」が墨下絵を描画し、版木の「彫り師」が下絵をもとに版木を彫刻して、色別の版木を作ります。その後、「刷り師」が版木をもとにして刷りますが、色の指定は絵師が指導することがあります。作品は、最終的に「版元」を通じて販売されます。 |