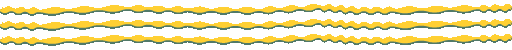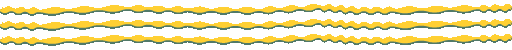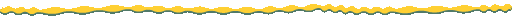
・LEDの基礎
物理的解説
LEDはLight Emission Diodeの頭文字をつなげたもので,直訳すれば「光を放つダイオード」ということである.
ダイオードはP型半導体とN型半導体を接合させたもので,電流はPからNには流れるが,NからPへは流れないという特性がある
(電子の流れから言えば,電子がNからPへの一方通行ということ).このときPとNの接合部を電流が流れる時,
ある程度(通常のシリコンダイオードの場合,0.5〜0.7V程度)以上の電圧をかけないと電流が流れない.
この電圧は,整流回路としてみた場合はロスになってしまうため,大電力の整流回路では電圧ロスの少ないショットキーダイオードや,
最近ではパワーMOS-FETをスイッチとして使用したアクティブ整流回路を用いることが多い.
さて半導体の材質や不純物の混ぜ方によってこの電圧は変わるのだが,材質によってはこの電圧に応じた電磁波が出るものがある.
たとえば1Vのギャップがあったとすると,電子がそこを乗り越えた時に放射される電磁波のエネルギーは1eV(1電子ボルト)になる.
1eVの電磁波というのは波長にすると約1.24μm程度の赤外線である.ではギャップが2Vになるとどうなるだろうか?
そうするともちろんエネルギーが2eVの電磁波が出るわけだが,2eVの電磁波というのは波長にすると620nmのオレンジ色の可視光線なのである.
これがまさにLEDの原理にほかならない.この電圧ギャップを作り出すために種々の材質の半導体が使われ,
接合部の形状を工夫するなどでより効率よく光を出すことができるようにしたのが,現在,市販されているLEDなのである.
さらに詳しく知りたい方は,たとえば
東芝のLEDデータブック
などを読んでください.
特徴
白熱電球がエネルギーを光に変える効率は1%以下と言われており,残りの99%以上は熱として周囲に逃げていってしまうが,
最新の超高輝度LEDでは効率は6%にもなるという.このため消費電力が少なくてすみ,熱的な問題が少ないことから小型化も可能であり,
また理論的には寿命は半永久的なので交換の手間がかからない,といった長所を持つ.短所としては,
絶対的な光量が足りない,青色を作るのが困難,コストが高い,ということがあるが,
現在では青色でも5000mcdを越えるものが出回ってきており,値段も安くなってきている.
青色LEDと蛍光物質を組み合わせることで純白色のLEDも登場してきており,また赤・緑・青の発光部を一つのパッケージにおさめ,
三原色を任意に発光させられるような製品もある.
用途
用途としては,従来からパイロットランプなどの各種インジケータに用いられることが多かったが,
超高輝度LEDの登場により信号機や自動車のハイマウントストップランプなどにも使用されるようになってきた.
また青が安定して供給されるようになったため,カラー表示可能なLED式の電光表示板も街中でよく見かけるようになった.
照明用として用いるにはまだ明るさが足りないようだが,それでも赤,緑,青のLEDを多数並べて,
マイコン制御により1600万色を任意のパターンで発光できるような照明装置が試作されている.
今後もLEDが用いられる場面はさらに増えていくと思われる.
どのくらい明るいか
5000mcd程度のLEDを点灯させた場合,LED1個だけで,1.2Wのメーター球よりも明るく感じる.
5W球にはまだまだ届かないが,10個程度つなげれば対等になるのではないだろうか.
ブレーキランプとして用いるには,100個程度が必要と思われる.日産グロリアに採用されたLED式テールランプの場合,
片側につき88個のLEDを使用していた.
・LEDを点灯させる
基本的な点灯回路
電球であれば,たとえば100Vの電球なら100V,12V用なら12Vにそのままつなげば点灯するが,LEDの場合はそういうわけにはいかない.
LEDの電圧というのは発光色によって決まる固定した値であり,通常は1.8V(赤)〜3.6V(青)くらいである.
しかもLEDにかける電圧と流れる電流との関係は,ある電圧までは電流はほとんど流れず,その電圧を超えると急激に電流が増える,
という非線形な特性を持っている.つまり1.8Vで20mA流れるLEDを5Vに直結すると,電流は約3倍の60mAではなく,
おそらく数Aの電流が流れてLEDが焼けてしまうだろう.従ってLEDを点灯させる場合には電流制限抵抗が必須である.
もっとも簡単な,1個のLEDを光らせる場合について考えてみよう.
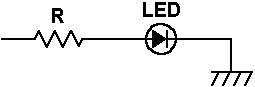 図中の抵抗器(R)の大きさを求めるには,まずLEDにどれだけの電流を流すかを決めなければならない.
通常,LEDの推奨動作電流は1〜20mAであり,特別な条件がないかぎりは20mAにすることが多い.
LEDに20mA流すために必要な電圧はLEDの発光色によって異なるが,ここでは白色LEDの例だとカタログ値は3.6Vとなっている.
そうすると,電源電圧12V,LEDにかかる電圧が3.6Vなら,抵抗器にかかる電圧は8.4Vとなり,
8.4Vで20mA流れるための抵抗値は420Ωとなる.実際には車の場合,走行中の電源電圧は13.5V程度のことが多いので,
その場合は抵抗器にかかる電圧が9.9Vなので,電流を20mAに抑えるための抵抗値は495Ω(実際に入手可能な抵抗器で,
これに一番近い値は510Ω)となる.
図中の抵抗器(R)の大きさを求めるには,まずLEDにどれだけの電流を流すかを決めなければならない.
通常,LEDの推奨動作電流は1〜20mAであり,特別な条件がないかぎりは20mAにすることが多い.
LEDに20mA流すために必要な電圧はLEDの発光色によって異なるが,ここでは白色LEDの例だとカタログ値は3.6Vとなっている.
そうすると,電源電圧12V,LEDにかかる電圧が3.6Vなら,抵抗器にかかる電圧は8.4Vとなり,
8.4Vで20mA流れるための抵抗値は420Ωとなる.実際には車の場合,走行中の電源電圧は13.5V程度のことが多いので,
その場合は抵抗器にかかる電圧が9.9Vなので,電流を20mAに抑えるための抵抗値は495Ω(実際に入手可能な抵抗器で,
これに一番近い値は510Ω)となる.
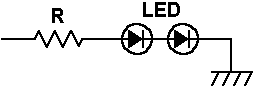 同じように白色LEDを2個直列で点灯させる場合は,13.5V,20mAという条件では抵抗値は315Ωになるから,
実際には330Ωの抵抗器を用いることになる.
同じように白色LEDを2個直列で点灯させる場合は,13.5V,20mAという条件では抵抗値は315Ωになるから,
実際には330Ωの抵抗器を用いることになる.
定電流回路
さて,上のように単に抵抗器を直列につなぐだけだと,自動車のように電源電圧が走行状況によって変化するような環境では,
電圧変動に伴って明るさが変化してしまい,あまりうれしくない.通常の電球でも,エンジン回転が不安定な状況だと,
少し明るさが変動するのがわかるが,LEDは電球より非線形な特性なので,さらに明るさが大きく変化する可能性がある.
すなわち,電球の場合は電流が増える(フィラメント温度が上がる)とフィラメントの抵抗が増加して,
結果的に電圧が上昇しても電流はあまり増加しないのであるが,LEDの場合は逆で,
わずかに電圧が上昇しただけで電流は急激に増加してしまうのである.
このため定電流回路をつけたかったのだが,簡単な方法が思いつかず困っていたところ,ふと可変シャントレギュレータ
(LM317L)
のアプリケーションノートを見てみると,定電流源として使用する方法が書いてあった.
これはLM317LのVOUT-ADJ端子間の電圧が1.25Vになるようにコントロールされることを利用して,
VOUTから62Ωの抵抗を介してADJおよび負荷に接続すると,
1.25V÷62Ω=20.1mAの定電流源として使用できるのである.
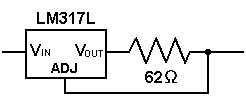 たいていのLEDは順方向電流の定格が20mAであるからちょうどよい.
これによりバッテリー電圧が変動しても一定の電流(明るさ)をキープすることができるようになる.
部品は下の回路図のようにLM317Lと抵抗器1本ですむし,価格もLM317Lが1個¥100,抵抗器は1個¥5だから高いものではない.
LM317Lは小信号用トランジスタと同じパッケージなので,サイズもコンパクトにできる.
電圧としては,LM317LのレギュレーションにはVIN-VOUTが約3V以上が必要で,
抵抗で1.25Vが使われるため,トータルとして最低でも4V以上のドロップがある.このため12V電源の場合,直列に接続できる限界は,
赤や黄色の場合は3個,青や白の場合は2個まで,ということになる.
たいていのLEDは順方向電流の定格が20mAであるからちょうどよい.
これによりバッテリー電圧が変動しても一定の電流(明るさ)をキープすることができるようになる.
部品は下の回路図のようにLM317Lと抵抗器1本ですむし,価格もLM317Lが1個¥100,抵抗器は1個¥5だから高いものではない.
LM317Lは小信号用トランジスタと同じパッケージなので,サイズもコンパクトにできる.
電圧としては,LM317LのレギュレーションにはVIN-VOUTが約3V以上が必要で,
抵抗で1.25Vが使われるため,トータルとして最低でも4V以上のドロップがある.このため12V電源の場合,直列に接続できる限界は,
赤や黄色の場合は3個,青や白の場合は2個まで,ということになる.
もう少し簡単な実現方法としては,定電流ダイオードを用いる方法がある.これは文字通り,
かかる電圧が変化しても流れる電流は一定であるというものだが,店頭で見たところでは最大で15mAのものまでしか売っていない.
LEDは20mAで使うことが多いので,ちょっともったいない(LEDの能力を使い切っていない,という意味で)気はするが,
何しろ定電流ダイオード1本を直列でつなぐだけ,という簡単さは特筆できる.あまり明るさを要求されない,
キー穴照明やインパネ周りのイルミネーションには向いているかもしれない.値段は,
大阪・日本橋の共立電子産業店頭で,15mA品が70円,10mA以下は100円(需要の差か?)だった.
ただし,定電流ダイオードは電圧ドロップが5V以上あるらしいので,白色LEDの場合は1回路につきLEDを2個直列が限度である.
定電圧回路
定電流回路の場合,LEDの数が増えると,定電流回路も同じ回路数だけ増やす必要がある.たとえば白色LEDを12個光らせようと思えば,
1回路についてLEDは2個直列が限度であるから,6回路分の定電流回路が必要になってしまう.
コスト的なこともあるが,設置スペースが大きくなってしまうという問題もあるので,
このような場合には定電圧電源から固定抵抗で各LEDに分配する方法が考えられる.白色LEDを2個直列にする場合だと,
電圧が7V以上,必要であるから,定電圧電源は8V以上が必要である.一方,バッテリー電圧が11V程度でも点灯する必要があるため,
電圧はあまり高くできず,現実には8Vが最も適当であろう.具体的には78M08を使用して,
各LEDには51Ω程度の抵抗で分配すれば,ほぼ20mA程度になるであろう(青色・白色LED使用時).
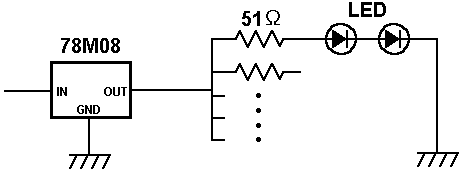 これだと78M08が¥60くらい,抵抗器が1個¥5であるから,12個点灯時(6回路並列)でもコストは¥90程度におさまる.
ただし,三端子レギュレータの電力損失には注意が必要である.12個点灯時でオルタネータ電圧が14.5Vの場合を考えると,
三端子レギュレータの電圧降下が6.5Vあり,12個点灯(6回路並列),1個あたり20mAの条件だと,電流のトータルは120mA,
したがって三端子レギュレータの電力損失は780mWになる.これは放熱器なしで使用できる上限ぎりぎりのため,
実際には小さい放熱板を追加した方がよいと思われる.
これだと78M08が¥60くらい,抵抗器が1個¥5であるから,12個点灯時(6回路並列)でもコストは¥90程度におさまる.
ただし,三端子レギュレータの電力損失には注意が必要である.12個点灯時でオルタネータ電圧が14.5Vの場合を考えると,
三端子レギュレータの電圧降下が6.5Vあり,12個点灯(6回路並列),1個あたり20mAの条件だと,電流のトータルは120mA,
したがって三端子レギュレータの電力損失は780mWになる.これは放熱器なしで使用できる上限ぎりぎりのため,
実際には小さい放熱板を追加した方がよいと思われる.
上の回路の場合,いずれにしてもバッテリー(オルタネータ)電圧に対し,定電流回路でのドロップ電圧が大きいため,
あまり効率が良くない.効率を上げようとすれば,1回路につき2個ではなく3個のLEDを光らせるようにしないといけない.
青色・白色LEDの場合,1個あたりの電圧降下が3.6V(IF=20mA時)なので,
3個直列の場合は10.8Vが必要である.汎用の三端子レギュレータだと10Vの次は12Vであるが,
標準的な自動車のオルタネータ電圧(13.5V前後)とバッテリー電圧(12.6〜13.2V)での使用を考えると,
標準の78シリーズの場合は最低でも2V以上のドロップがあるので,あまり適当ではない.
店頭で調べてみると,ドロップが0.6Vの78DL12が売っていた.これだとIGN OFF時にも,ほぼ問題なく点灯させることができそうだ.
電流制限抵抗は,(12.0-10.8)÷0.020=60 なので62Ωが適当かと思われる.
これを回路図にすると,次のようになる.
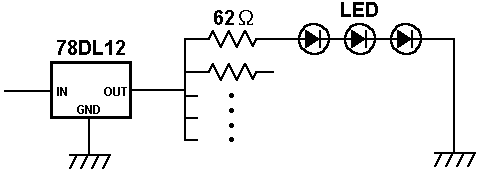 これだと12個点灯時(4回路並列)でオルタネータ電圧が14.5Vの場合で計算すると,三端子レギュレータの電圧降下が2.5Vであり,
4回路並列で約80mAの消費電流になるので,三端子レギュレータの電力損失は約200mWとなり,
これなら放熱器なしでもまったく問題なく使用可能と思われる.ただし,バッテリー電圧が12.6V以上でないと,
出力電圧が12Vを維持できないので,エンジン停止時には他の負荷のON/OFFにより明るさが変動する可能性がある.
78DLxxの出力電流は250mAまでなので,1回路20mAだと約12回路,36個のLED(青・白の場合)を光らせることができる.
これだと12個点灯時(4回路並列)でオルタネータ電圧が14.5Vの場合で計算すると,三端子レギュレータの電圧降下が2.5Vであり,
4回路並列で約80mAの消費電流になるので,三端子レギュレータの電力損失は約200mWとなり,
これなら放熱器なしでもまったく問題なく使用可能と思われる.ただし,バッテリー電圧が12.6V以上でないと,
出力電圧が12Vを維持できないので,エンジン停止時には他の負荷のON/OFFにより明るさが変動する可能性がある.
78DLxxの出力電流は250mAまでなので,1回路20mAだと約12回路,36個のLED(青・白の場合)を光らせることができる.
この上の回路を実際に組んでみたのだが,実測ではLED1個あたりの電圧降下が20mA時に3.4V程度になり,
このため12Vをかけたときの回路電流が30mA近くになった.青色/白色LEDの絶対最大定格は30mAなので,
ちょっと余裕がなさすぎるように思われた.自動車内は温度や振動など,非常に過酷な条件であるので,
もう少し電流を減らすために電流制限抵抗を82〜100Ωにしたほうが安全のように思われた.
また,78DLxxはドロップ電圧を少なくするため内部回路の出力段がPNPトランジスタのコレクタフォロア
(普通の78シリーズはNPNトランジスタのエミッタフォロア)なので高周波特性が悪く発振しやすいらしいのだが,
今回は負荷の変動はまったくないので,最初は発振防止用コンデンサをつけていなかった.
ところが,これだと出力電圧がちゃんとレギュレートされず,たとえば入力に15Vかけると,
出力にも15Vがそのまま出てきてしまうような有様だった.そこで試しに発振防止用コンデンサをつないでみると,
ちゃんと出力が12V付近に落ち着いた.すばらしい.たとえ直流負荷であっても,発振防止用コンデンサは必要なのね.
しかも,この発振防止用コンデンサは,レギュレータICにできるだけ近づけて配置しないと効果がない.
テスト回路では,レギュレータICとコンデンサを20cmほど離してみたところ,コンデンサがあるにもかかわらず発振してしまった.
なので,実際に回路を組む時には,最短距離で配線するように気をつける必要がありそうだった.
というわけで改良した回路が下の図である.
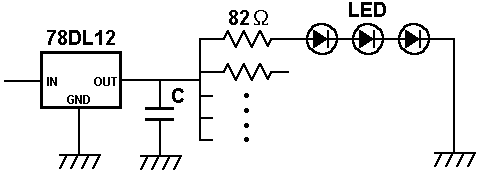 図中のCであるが,当方ではサイズの問題から0.33μFの積層セラミックコンデンサを使用しているが,
特に問題はないようである(もう少し容量を大きくした方がより安全だとは思う.LEDが多い場合は1μFを使用してみた).
これで回路を組んで実測すると,LEDに流れる電流は22〜24mA程度に落ち着いた.78DLxxの場合,
ドロップ電圧は最大0.6V以下となっているが,テスト回路(4回路並列・・約90mA)ではドロップ電圧は0.2V程度だったので,
通常のバッテリー電圧(12.6V前後)で十分に定格の明るさとなるようだ.
図中のCであるが,当方ではサイズの問題から0.33μFの積層セラミックコンデンサを使用しているが,
特に問題はないようである(もう少し容量を大きくした方がより安全だとは思う.LEDが多い場合は1μFを使用してみた).
これで回路を組んで実測すると,LEDに流れる電流は22〜24mA程度に落ち着いた.78DLxxの場合,
ドロップ電圧は最大0.6V以下となっているが,テスト回路(4回路並列・・約90mA)ではドロップ電圧は0.2V程度だったので,
通常のバッテリー電圧(12.6V前後)で十分に定格の明るさとなるようだ.
注:自動車用として用いる場合,万が一のバッテリー逆接続や,
オルタネータ故障時の過電圧に対する保護として,入力に保護用のツェナダイオードを入れておくことが望ましい.
ツェナダイオードの電圧は,12V車の場合は18〜20Vあたりが適当ではないかと考えている.
さらに明るくするには
LEDの場合も,いちおう電流を増やせば1個あたりの発光量は増える.たとえば多くのLEDの場合,推奨動作電流が20mAなのに対し,
絶対最大定格としては50mAまで流せるようになっている(青色や白色は30mAまでなので注意).
こうするともちろん明るくはなるのだが,たとえば電流を40mAにした場合,20mAのときと比べて,
電流は2倍だが明るさは1.6倍くらいにしかならず,端子電圧は上昇しているので消費電力としては2倍強となっており,
つまりエネルギー効率が悪い.従って1個のLEDに2倍の電流を流すより,同じ電流で2個のLEDを光らせる方が明るく,
消費電力も少なくなるのである.多くのメーカで推奨動作電流が20mAであるのは,こうした理由からだと思われる.
ただし,その分,多くのLEDが必要になるのでコストアップになる.日産グロリアのLEDテールランプが,
計算では約50mA流しているようなのだが,これは製造コストの問題で,自動車用としては電力効率よりもコストをとったということだろう.
・実際の製作例
室内灯のLED化
マップランプやルームランプ内に,白色LEDを追加して,明るく,より白く光るようにしようという計画.
問題は,8Wや10Wというランプに対し,LEDを追加してどの程度,明るくなるかということである.
30個くらいつければ,10Wの電球よりも明るくなりそうな感触はあるが,白色LEDが1個250円するから,
LEDだけで1万円近い値段になる.う〜ん.なお,ルームランプに関しては,蛍光灯にするという選択枝もあり,
これは画期的に明るくなるらしい.トヨタ車の場合,ハイエースに搭載されていた蛍光灯式のルームランプが,
ほとんどポン付けで流用可能のようだ.ただ,蛍光灯だとユニットが大きくて,天井からかなり出っ張ってしまう.
ミニバンなら問題ないのだろうが,天井の低いセダンの場合はちょっとどうかな,というところもある.
純正形状のままで蒼白かつ明るくできるLEDも捨てがたい(工作が大変だが).
→というわけで,実際にLED化してみた記録が,こちら.
結局,48個を集積することに成功した.なかなかの明るさだが,かかった値段も約13000円になった.
同様に,マップランプもLED化してみた(→記録はこちら).
こちらも36個×2のLEDを集積している.消費電力も,ルームランプが5W弱,マップランプが7W強なので,
合わせて約12Wと,純正の10W×3の半分以下に抑えられている.明るさでは,さすがに17Wの蛍光灯には勝てないが,
色の白さでは昼光色の蛍光灯に勝っている(LEDと見比べると,蛍光灯は黄色っぽく見える).
また,実際に蛍光灯にしているオーナーの話を聞いてみると,蛍光灯はドアの開け閉めでON/OFFを繰り返すと寿命がかなり短くなるので,
ふだんは切っていることが多いのだそうだ.LEDはON/OFFによる寿命低下は皆無なので,
そのあたりの心配は全くない.そういう意味では蛍光灯より実用性は高いかもしれない.
ドアカーテシランプ
ドアの内側についているドアカーテシランプもLED化してみた.詳細はこちら.
これは片側12個と控えめ(?)だが,それでも純正より断然,明るいし,ミラクルホワイトの電球よりもずっと青白い.
ただ,値段も両側合わせると約6500円かかってしまうが.さらに後席ドアにもドアカーテシランプを追加しており,
夜間の荷物の出し入れなどの際にかなり便利になった.
リヤライセンスランプ
あと,リヤのナンバー灯(リヤライセンスランプ)もLED化するとおもしろいかもしれない.
白色LEDを使えば,通常の電球より圧倒的に青白い光が出るから,よりナンバープレートが引き立つものと思われる.
→というわけで,実際に作ってみた記録がこちら.
なかなか目立っていてよいかもしれない(目立ちすぎて,ちょっと恥ずかしいくらいなのだが).
ただし軽自動車の場合は,ナンバープレートの地が黄色なので,電球の方が似合っているような気がする.
最近,字光式ナンバーでも,以前からの光源が電球のタイプに加えて,光源がLEDやELのものがあるという.
まだ実物を見たことがないのだが,一度,見てみたい気はする.
・今後の予定
リヤコンビランプ
すでに鉄道車両では尾灯や急行灯はLEDが当たり前になったが,自動車では新型グロリアや一部の外国車に例があるものの,
コスト的な問題のためかハイマウントストップランプ以外での採用はほとんど進んでいない.幸いというか,
マークIIではリヤコンビランプに関して,ランプ切れ検知装置というのがついており,
どれかランプが切れるとメータ内の警告ランプが点くようになっている.そこで解体車からこれを外してきて,
中の基盤をLEDのコントロール回路に入れ替えてしまおう,とたくらんでいる.問題は,大量のLEDが必要なこと(全部で数百個?)と,
これだけの数のLEDを点灯させるには,昇圧回路をつけたほうが効率がよくなると思うので,そういう回路も必要だし,
またバックランプは電球のままになるため,熱的に大丈夫かどうかということもある.
回路的には,PICを用いて高周波点灯を行うと同時に,
ドットマトリックス制御によりテールランプ/ブレーキランプの切り替えを行う予定.
(↑上の章で述べたように,効率を極限まで高めた現在の超高輝度LEDの場合,
電流が2倍になっても明るさは1.6倍くらいにしかならないので,低輝度のLEDと違って高周波点灯してもかえって暗くなってしまう.
したがって,直流点灯で,リレーにより電流制限抵抗を切り替えるか,
配線パターンによりテールランプ時も点灯するものとストップランプ時のみ点灯するものにわけるか,という方法になりそう)
グローブボックス照明
助手席の前にあるグローブボックスにも照明があって,スモールランプに連動して,蓋を開けた時に光るようになっているが,
この照明に関しては定格が1.4Wである.この程度だと,LED 1個でほぼ同等かそれ以上の明るさになるので,
効果は高いと思われる.また,もともとの照明の位置では,物をたくさん入れると役に立っていないことが多いので,
もう少し入り口近くから照らすような方法を考えたほうがよいだろう.向きはできるだけ前方(グローブボックス内部)
を照らすようにしておかないと,夜間,運転中に開けた時に光が直接,目に入るとまぶしいから気をつけよう.
ガラスエッジ照明
ハードトップ車の場合,ドアを開けた時にガラスの縁がむきだしであるわけだが,
一部の車でこのガラスの縁が光るようになっているものがあるらしい.
これは,窓ガラスの下端にLEDをとりつけてガラス内部を照らすようにすればいいはずである.
ただ,それにはドアをばらさないといけないのと,このLEDは雨水がかかるため,防水をどうするか,
あるいは窓ガラスは上下するので,その際に周囲に引っかかったりしないように配線するのはどうやるのか,
など解決すべき問題がある.
新車のオプションで,ドアを開けた時に座席の足下部分の照明がつくものがある.市販品でもLEDを使用したものがあるが,
これは電池とスイッチを組み合わせであるので,ちょっと抵抗がある.
どうせならドアカーテシランプの配線から分岐させれば電池やスイッチは不要となるので,そういう方向で考えている.
|