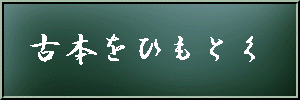
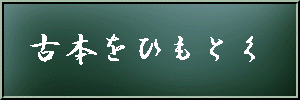
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
表・見返しイラスト 「記録に登場する 親族の系図」 |
砂沢 クラ・著 この本は、北海道新聞に一年間にわたって連載されていたものを単行本化したものです。当時私は道新を購読していませんでした。勤め先や散髪屋などで飛び飛びに読んで、アイヌの人たちに思いを馳せ、小学生のころ同級だったアイヌの少女のことを考えていました。単行本になったのを知ったのは84年の年が明けてからのことです。即座に購入したのは言うまでもありません。「小学校を退学する」の項を読んで少女のことが思い出され、何故か涙が込み上げたことを覚えています。 小学三年の頃、同級にアイヌの少女がおりました。寡黙で、と言うより全く口を利かず、無表情でただ座っているだけです。やがて学校へも来なくなりました。私達は無意識のうちに差別していたのかもしれません。学芸大出たての熱血青年教師だった担任の「級友みんなの力で学校へ来るよう説得しよう」という話で、日曜日に私を含め五人が少女の家へ向かいました。子供の足で学校から優に一時間はかかる距離です。集落ではなく、葦葺きの小屋が一軒あるのみ。小屋の周囲にわずかばかりの畑があり、老夫婦とおぼしき二人が農作業中で、幼子を背負った少女が傍にしゃがみ込んでいました。私達は近付いて、もじもじしながらも「学校で皆と遊ぼうよ」などと台詞の棒読みみたいな事を言い、説得しているつもりでした。少女はいつもの様に黙ったまま五分も過ぎたでしょうか、ふいに「行かれね。子守りある」とはっきりと言い切って小屋の中に消えました。初めて聞く少女の声に、五人とも息を呑み立ち尽くすだけでした。我が家も貧しい生活でしたが、少女の家はそれ以上に貧しいのだということが、子供の目にも分かりました。後で知ったことですが、少女の両親は出稼ぎに行って一年もたつとのことでした。 帯には「アイヌのフチ(おばあさん)の明治、大正、昭和の三代にわたる苦難の生活史。北海道の大自然の中で、神々を信じて暮らしていたアイヌの人たちの生活、そして明治以降の北海道開拓の歴史の中で独自の文化や伝統、生活習慣がどのようにして奪われていったかが、さし絵を添えて克明に書かれている」とあります。それがこの本の内容の全てです。 |
![]()