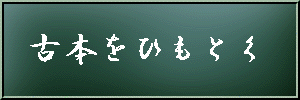
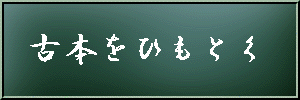
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
|
編集代表者・山本 三生 購入年月日は定かではありませんが、デパートの古書展で買ったものです。元来、地理学などに微塵も興味のなかった私ですが、この一冊だけがバラで売られていて、「北海道・樺太篇」の文字につられて手にしたのでした。樺太は私が満一歳まで住んでいた所ですが、ほとんど記憶は無く、両親の話を聞いても全くイメージできない場所でしたから、「樺太はどんな所だったのか」の思いで手にしたのだと思います。大判の本(26.5×19×3.5センチ)で500ページほど。九割がたが写真と図版です。 函館方面、室蘭地方、小樽方面、札幌方面、旭川方面、留萌・稚内方面、宗谷・網走方面、帯広・釧路・根室方面、千島地方、樺太南部方面、樺太中部方面、樺太北部方面と地方別に掲載された写真から、大正末−昭和初期の豊富な人文地理情報を読み取ることができます。写真解説者は帝大教授など錚々たるメンバーで、中に巌谷小波、河東碧梧桐、土岐善麿、三宅やす子、丸山晩霞らの名も見えます。 「日本地理大系」の巻立ては次の通り。第1・2巻 総論篇 自然地理・人文地理、第3巻 大東京篇、第4巻 関東篇、第5巻 奥羽篇、第6巻 中部篇 上,下巻、第7巻 近畿篇、第8巻 中国及四国篇、第9巻 九州篇、第10巻 北海道・樺太篇、第11巻 台湾篇、第12巻 朝鮮篇。別巻 第1 山岳篇、第2 満洲及南洋篇、第3・4 海外発展地篇 上,下巻、第5 富士山。 刊行順は未調査で分かりませんが、第10巻添付の月報が「第三号」となっており、月報内容から前回配本は第4巻関東篇、次回が第3巻大東京篇であることが分かります。また、毎月1巻の配本とありますので、初回配本は昭和4年12月だったと思われます。 |
![]()