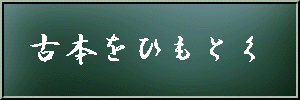
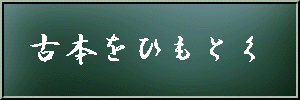
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
 「SF百科図鑑」表紙 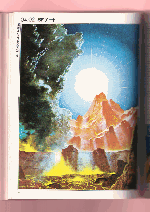 「SFアート」の項からチェズリイ・ボーンステル画 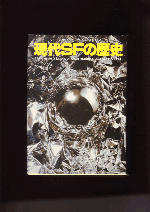 「現代SFの歴史」表紙 |
編 者:ブライアン・アッシュ ご存知の通り、SFはサイエンス・フィクションの略称。語源は米SF界の祖ヒューゴー・ガーンズバックの造語「サイエンティフィクション」。日本では空想科学小説と訳されましたが、二十数年前からファンタジー、ブラック・ユーモアなど多くの要素を含んでSFの範疇が拡大し、徐々に使われなくなりました。私がSFを読み始めたのは空想科学小説そのものの頃でしょうか。 私にとって、SFの入り口は映画でした。小学生の頃の「月世界征服」(原作ロバート・A・ハインライン「宇宙船ガリレオ号」)、「海底二万哩」(原作ジュール・ベルヌ「海底二万リーグ」)、「禁断の惑星」(原作A・ブロック、A・アドラー「禁断の惑星」)が火付け役。やがて「2001年宇宙の旅」(映画発端部の原作アーサー・C・クラーク「前哨」)、「惑星ソラリス」(原作スタニスワフ・レム「ソラリスの陽のもとに」)で大爆発です。 多読の時代は60年代後半から70年代。「SFマガジン」を定期購読し、古書店でハヤカワ文庫を漁ってまさに手当たり次第の濫読でしたが、そのうち内容がごちゃ混ぜになって頭脳混乱。過去の小説は系統立てて読まなければと思うようになり、SFの全容を体系づけて書いた本はないものかと探している時に出合った一冊です。 図版が多くSF百科ガイドととして楽しめます。ただ、内容的に英語圏が中心でフランス、ドイツ、ソ連、ポーランド、北欧などの作品記述は少なく、日本については皆無と言うのが残念なところです。それでも出版前年の1976年迄の状況を扱い、日本語版が78年にいち早く出たことがこの本の価値を物語っていると思います。84年、早川書房発行の学術的な著作「現代SFの歴史」を読む前に一読するか、参照・併読をお奨めします。 内容は、基礎SF史を年表化した第1セクション、SF小説の主要テーマ(「宇宙船と星間飛行」から始まり「イナー・スペース」まで19テーマを網羅)を概説した第2セクション、SFへの学究的アプローチの第3セクション、ファンダム(注:SF界の用語で、ダムはキングダムの意。熱狂的なSFアマチュア、SFファンの世界を指す)とメディア(アート、映画、テレビ、雑誌、単行本とアンソロジー、コミックス、評論と講座等)を扱った第4セクションの4部構成です。
|
バックナンバー|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
![]()