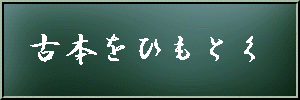
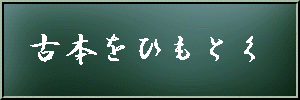
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
|
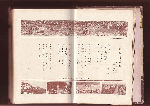 巻頭「札幌行進曲」の歌詞が載った見開きページ |
著 者:大塚 高俊 いつ、どこの古書店、古書展示即売会で購入したか、覚えていない。しかし、購入の動機ははっきりと記憶する。こうである。この本が出版された時、私はまだ生まれていない。発行年の1931年(昭和6年)と言えば、即座に柳条溝事件を思う。9月18日夜、満州・奉天郊外柳条湖で起こった満州鉄道爆破事件である。満州事変から15年戦争への幕開けとなる出来事だ。延々と続く愚行の始まりの年に出た本と言うのも面白い、が第一。「大札幌」と言う書名も豪気で気に入った、が第二。昭和初期の札幌を知る資料としても、いくらか役に立つかも、が第三の動機だった。 道史年表を見ると、昭和8年を挟んで2年連続4年間、本道は冷害凶作に泣いている。昭和5年の稲作は空前の豊作だったが、米相場は急落。生産農家は豊作貧乏を余儀なくされ、前年4年の世界大恐慌の影響もあって、世は不景気のただ中。この時期に、なぜ「大札幌案内」なのか。理由の一つは、6年7月12日から40日間開催された「国産振興北海道拓殖博覧会」に在りそうである。65万人を記録したという入場者を当て込んでの出版ではなかったか。 著者・大塚高俊は発行元・近世社の主で、中山晋平作曲「札幌行進曲」(日本ビクター)の作詞者である。自序に「我社壁頭(ママ)の出版なる意味に於て、我社史の第一頁に記さるべき存在に於て思出多き意義を持つ」とあり、近世社の初出版本であることが分かる。小学校の青年教師から転じた大塚が万全を期し、この機を狙っての起業、出版であったろうことは想像に難くない。表紙、扉ともに「大札幌案内」だが、背表紙だけなぜか「新版大札幌案内」とある。近世社に旧版があるわけもなく、既出版の同類本を意識しての初出版への気負いと意気込みが、そうさせたのかも知れない。 内容は実に多彩である。札幌の顔、札幌の印象、自然上の札幌、遊覧の札幌、享楽の札幌、学芸の札幌、神社・宗教、産業の札幌、藻岩山上の眺、各章。ほかに、札幌首府論、札幌建都史、市政展望、交通・警衛、社会事業、各章があり、当時の札幌の姿を概観するには十二分の記述である。例えば「享楽の札幌」の章は、デパート、劇場、映画常設館、カフエー、喫茶店、料理店、ダンスホール、の各項に分けて書かれており、巻頭「札幌行進曲」の『ジャズと五色の光の巷 こゝは薄野キネマ街 右は山鼻左にしよか 恋の十字路一思案』とある昔日の薄野界隈を散策できるだろう。 なお、札幌市南7条西5丁目で旗揚げした近世社のその後、出版・文筆に生きんとした大塚高俊のその後については未調査のため、私には分からない。
|
バックナンバー|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|||||||
![]()