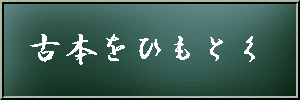
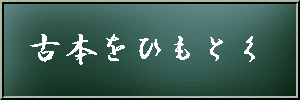
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
|
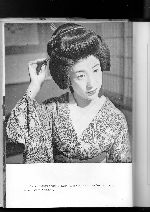 キャプションに「カエデの葉をあしらった着物は、彼女の名前“もみじ”に似つかわしい」とある |
著 者:P.D. PERKINS この本も前回紹介した「紅燈夜話・新橋三代記」と同時期に、デパートの古書市で購入したものです。「PONTOCHO」の題名を見つけて、東の芸者さんの事ばかり追いかけていた自分に気付き、西の代表・京都の芸者さんの事も勉強せねば片手落ちと思ったこと。西欧人が芸者さんをどう見ているか興味があったこと。表紙カバーの芸者さんの艶っぽさに魅せられたこと。この三点が購入動機でしたろうか、今となっては判然としません。内容が写真集みたいなもですし、巻末の語彙解説が面白く、横文字には弱い私にも理解できたので、大胆にも何とか読めそうだと考えての購入でした。その後は辞書を引き引きの飛ばし読みで、未だ未読の部分が残る一冊でもあります。 発行年の四年前に朝鮮戦争が勃発、三年前にはサンフランシスコ対日講和条約と日米安全保障条約の調印で、当時日本には大勢の米軍人及び軍関係者が住んでいましたから、それらの人々を対象に出版されたものでしょう。カバー折り返しにTOKYO NEWS SERVICE社(東京・銀座10西8)刊行の「日本庭園の千年」「日本昔話」「奇妙な風習と日本の礼儀作法」など日本関連書籍名が幾冊か載っています。「日本庭園―」の価格が2500円です。大学卒初任給七、八千円の頃ですから、日本人相手の商売でないことだけは確かです。 内容は、先斗町の佇まい、そこに生活する芸者さんたちの日常、鴨川をどりの様子(秋公演は98年が最後、現在は春だけとなりました)など写真を主体に追っています。目次は次の通りです。 ●著者序文抜粋● 日本の言葉の中で最も誤解されている言葉の一つは「芸者」である。欧米人はもとより日本人でさえ誤解している。語彙の定義づけでは定評のある「完全和英辞典」の編者・ブリンクリーによれば、「芸」という語は芸術・才芸を意味し、「者」は人を意味する。それゆえ「芸者」は才芸の備わった人を意味し、「芸妓」は才芸の備わった女性を意味する。……。この本の企画当初は広く「芸者」一般について書く予定だったが、それにはページ数が足りぬため、芸妓・芸者という語の典型とも言うべき先斗町の芸妓に絞り記述した次第である。先斗町には百人を超す芸妓、舞妓がいるが、この本で紹介したのはほんの一部である。もし時と所が許すなら、先斗町の住人になって、全員を取り上げてみたいと思う。 ●芸者の項「もみじ」抜粋● “もみじ”は春・秋の鴨川をどりの主役の一人だ。カエデの葉をあしらった着物は、彼女の名前“もみじ”に似つかわしい。“もみじ”は大阪で生まれ、五歳で山村流の踊りを習い、後に若柳流に変わった。小学校卒業後、宝塚劇場ダンシングスクールに入り、バレエ、タップ、アクロバットダンスを学んだ。“もみじ”を教えたロシア人の先生はとても厳しく、初め百二十人いた同級生も、予科コースを修了したのは半数だけだった。しかし、“もみじ”は予科一年間、専科一年間を終え、舞台に立って二年間の卒業後コースも修了している。同級生には有名女優の月丘夢路、音羽信子、越路吹雪がいる。十八歳で宝塚を去り、大阪・宗右衛門町で芸者になったが、一年で辞めた。戦争が終わり、“もみじ”は西川流の舞踊を習って師範となり、名取・西川もみじとなって先斗町の芸者となった。彼女の舞踊家としての成功は、春・秋の鴨川をどりで常に主役の座を与えられるという事実が証明している。……。“もみじ”は日本でも有名な芸者だが、彼女は客の地位や身分に関係なく、皆同じように気配りして、もてなすのだ。 |
バックナンバー|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|||||
![]()