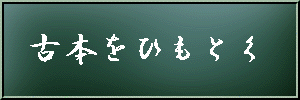
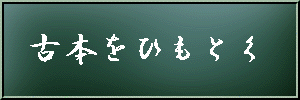
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
|
 「呪詛を放つ患部―見世物小屋編」の扉写真 |
著 者:鎌田 忠良 札幌祭りの折、創生川の川縁や中島公園にまだ見世物小屋がひしめいて、私もよく覗いていた頃の本ですから、見世物の様な生業は他にどんなものがあるのだろうくらいの興味で購入したものと思われます。見世物小屋の呼び込み口上とか、高田瞽女が唄う、性を描写した「へそ穴口説」とか、読み始めて面白いのですが、所々真っすぐに頭に入って来ない部分があって、生意気にも「下手くそな文章を書く奴だ」と思った記憶があります。 どんな内容の本か、と問われても一口では表現できません。ルポ、ドキュメントに違いなく、聞き書きでもあり、探訪記でもあるのですが、それだけではない何かを内包しています。帯に長部日出雄氏が記しています。「鎌田忠良は津軽へ遡行するのではなく、そこを出発点として流民芸を追いかけた。そして流民の<芸>と<生>の間にある深淵に着目し、<生>への唯一の回路としての<芸>という注目すべき視点に到達したのである」と。流民芸が、最下層(言葉が適切ではありませんが)で「生きる」と言う自覚を基点に成立するもの、との視点から捉えたルポと言ったらいいでしょうか。流民芸の哲学的?考察と言ったらいいでしょうか。奇妙な味わいのある一冊だと思いますし、「芸能」の意味を考える一助になることは確かです。 最終章「棄民の芸への照射――付編」で、著作の動機と流民芸に対する考えを長部氏の言う「注目すべき視点」で述べています。冒頭に「この二年余、……棄民(あるいは流民)の芸能つまりは、最下層にあって生きる人たちのなかにおける芸人・芸能について、考察を試みてきた。そして、その方法としてこの間、……ごく数日の短いタビをそそくさとくりかえしていた。なによりまず、それら棄民による芸人、また逆に、芸能において最下部に位置する人びとの姿、ありようとはなにか、それを直接自らの目でたしかめ、その肉声を耳もとにきくためである」とありますが、そうして成った一冊が「日本の流民芸」です。 ●目次は次の通り● 死児は方言で還る――津軽イタコ編/桟敷の闇の孤絶者――芝居小屋編/呪詛を放つ患部――見世物小屋編/漂泊の闇の津軽三味線――高橋竹山編/飢餓のうたの圧殺――津軽乞食唄編/め絵馬参り瞽女唄――杉本キクイ編/辺境遊芸への邂逅――猿倉人形芝居編/偏見の闇からの咆哮――浅草なにわ節編/異形の芸人原像――大道芸人窟編/仁義編伊六万歳――加藤竹三郎編/初発の芸の光芒――沖縄芝居編/日常の流民芸人の方へ――テント小屋美少女編/棄民の芸への照射――付編/あとがき |
バックナンバー|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15||||
![]()