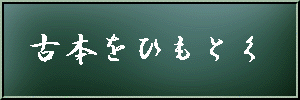
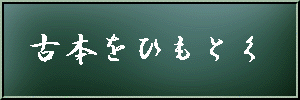
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
|
 「日本のヤクザ」表紙 |
著 者:井出 英雅 この本は「やくざ覚え書」(東都書房、1958年11月15日発行)に一部加筆した改訂版です。古書店で購入したことは間違いないのですが、購入日付の記入がなく、いつ頃のことか明確には分かりません。元版である「やくざ覚え書」を古書即売会で買い求めたのが1984年で、それよりずっと以前に「日本のヤクザ」(加太こうじ著、大和書房、1964年発行)と相前後して購入したはずなのですが……。 この類の本は、私の習性として映画に触発されて探し求める傾向がありますから、「仁義なき戦い」(1973年)の頃だったかも知れません。と言うのも、時代劇映画が好きで股旅物・侠客物は幾本も観ていますから、江戸期やくざの態様を知るために田村栄太郎著の「やくざの生活」(雄山閣)、「一揆雲助博徒」(三崎書房)などは既に読んでいて、「日本侠客伝」(東映、1964−71年)、「昭和残侠伝」(同、1965−72年)あたりまでは新知識を必要としなかったのですが、「仁義なき戦い」は全く違っていたからです。終戦後の話、しかも実録と銘打たれていましたから、「今までのやくざとは違う。戦後のやくざって何だ」と言うことで新興やくざから暴力団への系譜をたどる本を探し始め、まず「日本のヤクザ」を見つけ、その後手に入れたのが「やくざ学入門」だったと考えられなくもありません。まあ、30年も前のことですから、確かなことは何とも言えません。 講談、浪曲、任侠映画に登場するやくざは皆々颯爽として格好良く、強きをくじき弱きを助けて女性に慕われる。任侠の世界に生きるのも悪くはないなあ、なんぞと夢想していたのは十五、六の頃でしょうか。現実のやくざの態様を見聞きすれば任侠道など遠い昔の夢のまた夢、憧れなんぞ抱きようもない世界です。復刻版「本邦侠客の研究」(尾形鶴吉著、西田書店、1981年発行)の推薦文に井上ひさし氏が「自分たちの先輩が庶民の代表であったことを知らず、金もうけや弱い者いじめにうつつを抜かしているかにみえるやくざ・暴力団の諸兄よ、ぜひこの本を読んで、庶民の核弾頭であった侠客精神を体得してもらいたい」と書いて当然。正統派やくざ“すじもの”既になく、侠客など望むべくもない今こそ“本物”のやくざについて学ぶ時かも知れません。 ☆ ☆ ☆ 前回、「実録北海博徒伝」を紹介しましたが、そも「博徒」とは何なのでしょうか。それを知るための本が「やくざ学入門」です。冒頭に「やくざとは博徒のことである。ふつう、ならずもの、または世のあぶれものをひっくるめてやくざという。が、博徒は自分の口からやくざとはいっても、無頼漢の総称にすぎないやくざものとは区別したがる」とあり、「後ろめたい日陰の暮しであって、『役に立たぬ』『性行のおさまらぬ人』でなかったら、とうていできる世渡りではない」から、「やくざみずから、『利口じゃできず、ばかじゃできず、中途半端じゃなおできず』といいならわしている」と書いています。やくざの「一」から教えてくれる「やくざ学入門」は、一般人では知り得ぬやくざ世界の内側を開示した書であり、やくざのしきたりをまとめた資料・史料としても貴重な本と言えます。 あとがきに、「この覚え書はもと、ひとえに志村九内親方の博覧強記によってなった。……NHK吉田直哉氏の縁が発表の機縁となったこともしるすべきだろう」とあります。実は、吉田氏は1957年11月から始まったNHKテレビドキュメンタリー・シリーズ「日本の素顔」で、上萬一家・志村九内親分の了解の下、親子の盃、近付き仁義、刺青、賭場など博徒集団の日常を捉えた「日本人と次郎長」を撮っていたのです。この一件は吉田氏の「映像とは何だろうか―テレビ制作者の挑戦―」(岩波新書、2003年6月発行)に詳しく、添えられた写真〈手打ちの式〉は「やくざ覚え書」の口絵写真と同じものが使われています。その時の縁で著者は吉田氏に出版社を紹介してもらい、翌58年に「やくざ覚え書」を世に出すことができたのでした。 《「やくざ覚え書」掲載の著者略歴》 大正2年、富山に生る。血縁うすく信州、横浜等の縁辺に育つ。学歴6箇所に約4年。昭和4年、客気にかられてぐれ出し、念々動揺定まるところのないままに各地を転々、18年発心して僧堂に入るも、生悟りはたちまち地金あらわれ、21年、再び濁世にまみれるうち、積悪の報いか病床に起臥して今日に至る。 「覚え書」はハードカバー、口絵写真付き。「入門」はペーパーバックスで口絵もありませんが、本文中に幾枚か挿入されています。写真は両本とも同じ場面を撮ったものですが、撮影位置などが違っています。章題はほとんど同じで、「覚え書」の章題が「入門」の副章題になっています。「入門」の最終章「裏街道のことば――ときあかし」が新たに加わった部分となります。 ◇……………◇ ◇……………◇ 《「やくざ学入門」目次》 やくざ談義/欲に走らぬ自負―その日常/自虐に咲く花―刺青/賭博師の戦場―丁半/松と牡丹の紋様―バッタ/犠牲の宣誓―親子の盃/渡世の飲み分け―兄弟の盃/さらし木綿と匕首―服装/渡世のテスト―近づき仁義作法(「やくざ覚え書」の一宿一飯、旅人行法を含む)/無職渡世の顔―縄張り/渡世の勘当―破門(「同」の指をツメルを含む)/斬り込みの発端―マチガイ(「同」の殴りこみを含む)/水に流すしこり―手打ち/花環が描く顔―弔い次第/渡世との惜別―引退/一家の束ね―跡目相続/任侠の純粋培養―すじもの/裏街道のことば―ときあかし/あとがき 《「日本のヤクザ」目次》 ヤクザの世界:ヤクザ、博徒―、テキヤとグレンタイ、ヤクザの心理/ヤクザと私:よき時代の粋な鳶職人、戦争と貧困の犠牲者、ヤクザの中のヤクザ、純情型の女たち、博打うち親子三代/ヤクザ物の位置:ヤクザ物講談、ヤクザ物演劇、ヤクザ物浪花節、ヤクザ物歌謡曲、ヤクザ物映画、日本音楽と東京落語/賭博のすべて:賭博のおもしろさ、サイ賭博と牌賭博、賭博のイカサマ/繁栄するヤクザ:ヤクザの現況、ヤクザの資金源、ヤクザを育てる陰の力/ヤクザと社会主義者:貧困と社会の矛盾、体制変革と体制維持/あとがき |
バックナンバー|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
![]()