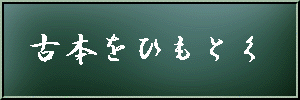
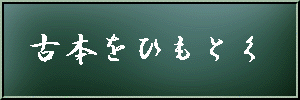
白い古書、ぞっき本も、時を経て読むと面白いものです。 |
| 今月の一冊は、これ! |
|
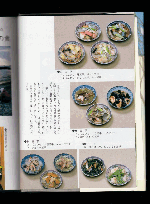 口絵〈道南松前の食〉から三平の写真。12種類の三平が載っている |
編 者:北海道新聞社 先日、西川潤著「世界経済入門・第三版」(岩波新書)を読み、日本の食料自給率の低さに唖然としました。1960年の80%程度が90年代には40%(カロリーベース)、穀物自給率は28%(2000年)で、日本輸入分のために、日本の耕地500万ヘクタールを上回る540万ヘクタールの外国の耕地が使われ、輸入畜産物のために更に500万ヘクタールも使用していると言います。作り手側が「日本には売りません」と言ったら、私たちには食べる物がないという状況です。農産物だけではありません。水産物も同様、スーパーへ行って商品に張られたラベルを見れば一目瞭然、産地が全世界にわたっていることが分かります。 元来、私たちは「地産地消」を基本に生活していました。それがなぜ、こんな状況に陥ってしまったのか、真剣に考えなければなりませんが、その前に北海道の食物を知ることも大事ではと思い「北海道食物誌」を紹介した次第です。現在では食料自給率既に40%以下のこの国で、「国産じゃなきゃ、地物でなけりゃ」なんぞと言ってられませんが、ありがたいことに広い北海道、見渡せば地物食材がいっぱいです。無論、この本に登場するのはほんの一部ですが、各種食物に恵まれているのが良く分かると思います。 また、北海道草創期から「地産地消」の生活の中で培われた食生活、食文化を知ることも必要です。私たちの父母や祖父母が何を食べて育ったのか、この風土に連綿と続く「食」の基盤がいかに出来上がったのか。それを知るための手掛かりとして「日本の食生活全集①聞き書北海道の食事」も併せて紹介したいと思います。 ☆ ☆ ☆ 「北海道食物誌」は1977年(昭和52年)の北海道新聞家庭面に連載された「北の食卓」を一部加筆補正し、翌年6月に発行されています。当時の一般家庭の食卓に上ったであろう四季折々の食材を、魚介類から野菜、山菜にいたるまで94種類紹介。食物誌としての故事来歴の記述はもちろんのこと、料理ガイドを添えて、下処理、保存法、食べ方、料理法まで教えてくれる重宝この上ない一冊です。今も時折引き出して読む、酒の肴づくりの私の参考書です。 《「北海道食物誌」目次》 〈春から夏の味覚〉フキノトウ/エゾニワトコ/ヤチブキ/ツクシ/エゾエンゴサク/フクベラ/カタクリ/アズキナ/ギョウジャニンニク/コゴミ/ドングイ/ボウナ/ヨモギ/タンポポ/ミツバ/ゼンマイ/ヨメナ/セリ/エゾイラクサ/ウド/シオデ/ギボウシ/ワラビ/アザミ類/タランボ/ハマボウフウ/トトキ/タケノコ/フキ/カンゾウ/アカシア/アスパラガス/梅/ニシン/マス/アカハラ/シマエビ/ソイ/アブラコ/ワカサギ/ホッケ/ヤマベ/マナマコ/ガヤ/ホタテガイ/ホッキガイ/ホヤ/昆布類/イカ/カニ/ウニ/ツブ/アワビ/ヒメマス 〈秋から冬の味覚〉トウキビ/ジャガイモ/大豆/インゲン/タマネギ/ユリ/キイチゴ/ボリボリ/ラクヨウ/シメジ類/エノキダケ/マイタケ/コクワ/マタタビ/コケモモ/キャベツ/カボチャ/リンゴ/クルミ/ブドウ/ダイコン/タコ/イワシ/サバ/サンマ/サケ/シシャモ/ハッカク/キュウリ/チカ/カキ/キンキン/メヌケ/カスベ/コマイ/カジカ/ハタハタ/タラ/カレイ/ヒラメ 〈四季の漬け物〉ダイコンを使って/ハクサイを使って/ミョウガを使って/キャベツを使って/粕漬けと味噌漬け/カブを使って/ニシンを使って/イカを使って/ピクルス/サケを使って/変わり漬け①/変わり漬け②/変わり漬け③/春から夏の漬け物メモ 毒キノコの見分け方/あとがき/索引 ◇……………◇ ◇……………◇ 「聞き書北海道の食事」は農文協(社団法人・農山漁村文化協会)発行の「日本の食生活全集」全50巻の第1巻として1986年4月に発行されました。編集は「日本の食生活全集・北海道」編集委員会(代表・矢島睿)です。 はしがきに「開拓の地に生きることは、その地に生える植物とともに生きることでした。……。北海道の食生活にとって、越年(越冬)のための食糧の確保は、欠かすことができません。……。開拓の地、北海道は、全国から集まった人びとのふるさと料理がにぎわう場でもあります。……。開拓、越年と並んで、北海道にはもう一つの顔、海があります。……。雄大な海と大地。この厳しい自然と対峙しながらそれをとりこみ、また、独特の洋食文化をも先駆的につくりあげていった北海道の食。その食文化における先人の魂、新天地に育んだ食と暮らしのフロンティアスピリット」とあり、聞き書の内容を端的に表しています。 《「聞き書北海道の食事」目次》 〈道東十勝の食――開拓地の動植物と共に生きる〉四季の食生活、基本食の加工と料理、季節素材の利用法、伝承される味覚、道東十勝の食、自然、農業 〈道東海岸の食――こんぶ漁に生きる浜〉四季の食生活、道東海岸の魚貝、海草料理、道東海岸の食をもめぐる暮らしぶり 〈道南松前の食――ふだんは何かというと「三平しょうか」〉四季の食生活、基本食の加工と料理、季節素材の利用法、伝承される味覚 〈西海岸にしん漁場の食――群来るにしんを追って〉四季の食生活、基本食の加工と料理、季節素材の利用法、伝承される味覚 〈道北(旭川)の食――北上する米、水田開拓の夢開く〉四季の食生活、基本食の加工と料理、季節素材の利用法、伝承される味覚 〈札幌の食――独自に発達した洋食〉〈人の一生と食べもの〉〈北海道の食とその背景〉〈北海道の食 資料〉 |
バックナンバー|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
![]()